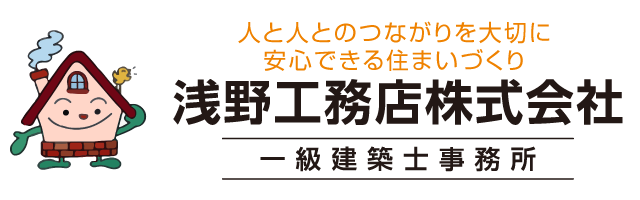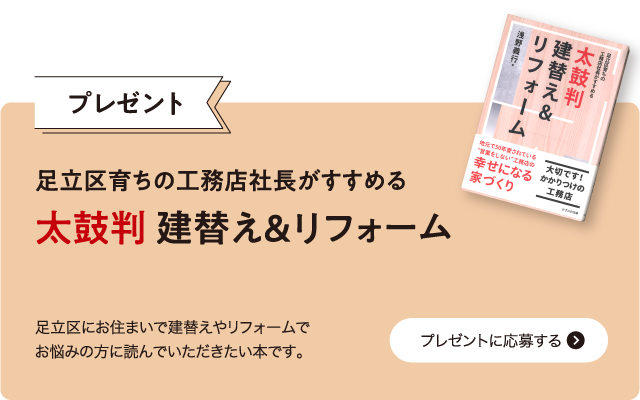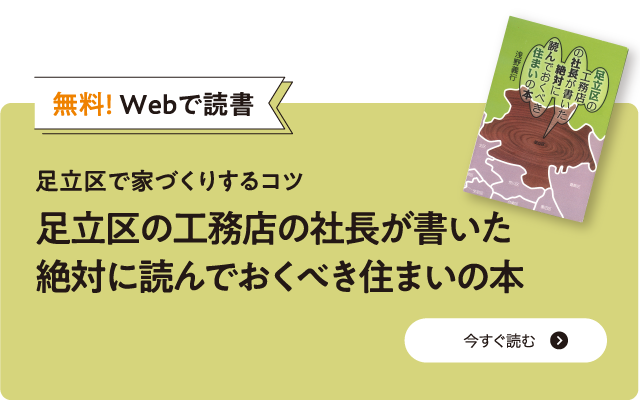家の性能よりも大切なこと|“住む人の想い”に寄り添う、目に見えない価値を実現する家づくり

近年、住宅を選ぶ際に「性能」を重視する方が増えています。
断熱性・耐震性・気密性など数値で比較できる性能は、暮らすうえでの安心や快適さを支える大切な要素です。
しかし、家づくりにおいて本当に大切なのは、「そこに住む人の想い」ではないでしょうか。
実際、性能が高いだけでは満足できない「住みにくさ」を感じるケースも少なくありません。
この記事では、住宅性能の基礎知識から、性能だけでは語れない「住まいの本当の価値」までを解説します。
さらに、自由設計を活かした施工事例や、地域密着の工務店だからこそできる家づくりの工夫もご紹介しますので、足立区で家を建てたいと考えている方はぜひ参考にしてください。
目次
1.目に見える性能とは?

家づくりにおいて、断熱性や耐震性などの「性能」は重要な判断材料です。
まずは、そうした「目に見える性能」の基本と、それぞれの基準や指標がどのように暮らしに影響するのかを確認しましょう。
(1)目に見える性能には基準や等級がある
まずは、主要な住宅性能とその基準を簡単に整理します。
① 断熱性
断熱性は、室内の暖かさや涼しさをどれだけ保てるかを示す指標で、断熱等級によって評価されます。
新築住宅では等級4~7から選べ、等級が上がるほど断熱性能が高く、光熱費の削減や快適性の向上につながります。
| 断熱等級 | 概要 |
| 等級4 | 次世代省エネ基準(2025年4月以降の最低基準) |
| 等級5 | ZEH水準(2030年以降、最低基準として義務化予定) |
| 等級6 | HEAT20 G2レベル(冬でも室温がおおむね13℃を下回らない) |
| 等級7 | HEAT20 G3レベル(冬でも室温がおおむね15℃を下回らない) |
住宅の断熱性能は、住む地域の気候や家族の生活スタイルに合わせて選ぶことが重要です。
基本的には、最低基準として2030年以降義務化予定の等級5を満たしていれば、生活するうえで問題ありません。
土地の形状によっては、希望の等級を必ず実現できるわけではないこともあります。
過剰な性能はコスト増にもつながるため、「必要な等級」を見極める視点は欠かせません。
② 耐震性
地震の多い日本においては、耐震性も住宅選びにおける最重要ポイントのひとつです。
住宅の耐震性能は耐震等級1~3で評価され、等級が高いほど、建物が揺れに耐えられる構造になっています。
| 耐震等級 | 概要 |
| 等級1 | 建築基準法が定める最低基準。数十年に一度の大地震(震度6強~7相当)で倒壊しない最低ライン |
| 等級2 | 等級1の1.25倍の耐震性能。学校や病院などの建物と同等 |
| 等級3 | 等級1の1.5倍の耐震性能。消防署・警察署など防災拠点にも使われる最高等級 |
等級3を取得するには構造設計の工夫や施工の精度が求められますが、費用の負担も増えてしまいます。
土地の形状によっては建物の形も影響を受けるため、構造上の制限がある場合もあり、希望の等級とならないことがある点にも注意が必要です。
断熱等級同様、「必要かどうか」の視点でよく検討し、選択することが重要です。
③ 気密性
気密性とは、住宅のすき間の少なさを示す性能で、空調効率や快適性に大きく関わります。
気密性の高さは「C値(相当隙間面積)」という数値で評価され、数値が小さいほど気密性が高いことを意味します。
| C値の目安 | 評価 |
| 2.0以下 | 標準的な気密性能(一般的な新築住宅の水準) |
| 1.0以下 | 高気密住宅の水準 |
| 0.5以下 | 超高気密住宅・パッシブハウス級の水準 |
気密性が高いと、冷暖房が効率的に働き、室内の温度が安定します。
また、外気の侵入を防げるため、花粉やホコリ、騒音対策としても有効です。
断熱性能とセットで考えることで、より快適な住まいが実現します。
④ その他の性能
住宅には、断熱・耐震・気密といった主要性能のほかにも、暮らしやすさや安心感を支えるさまざまな性能があります。
これらは一律の等級はありませんが、設計や設備の選択によって大きく差が出る部分です。
| 性能項目 | 目的 | 対策例 |
| 防音・静音 | 生活音や外部の騒音を遮る | 遮音性の高い窓や建材、防音下地を使用 |
| 防火・耐火 | 火災の被害を最小限に抑える | 耐火外壁材・石膏ボード・防火サッシなどを採用 |
| 調湿 | 室内の湿度を一定に保ち、結露やカビを防ぐ | 調湿性のある内装材・自然換気の導入など |
| 脱臭・抗菌 | 室内の空気を清潔に保つ | 抗菌建材の使用など |
これらの性能は住み心地の「質」に直結する要素です。
特に子育てや在宅ワークなど、生活スタイルに合った対策をとることで、より心地よい空間づくりが実現します。
(2)お金をかければ、性能の良さは無制限?
性能を高めれば安心感は増しますが、予算には限りがあるものです。
ここでは、コストと価値のバランスについて考えていきましょう。
① なくても困らない性能とは?
すべての性能にお金をかければいいというものではありません。
実際には「なくても困らない性能」もあり、過剰な仕様はコストの無駄になることもあります。
たとえば、寒冷地でない地域、あるいは狭小地での高断熱等級や、使わない部屋への防音施工などがその一例です。
また、家族構成や生活スタイルが変わることで、必要と考え導入した設備が数年で不要になるケースもあります。
「本当に必要か?」「ずっと必要か?」「何が重要か?」を考えたうえで取捨選択することが、後悔しない家づくりにつながります。
② お金をかけて後悔する性能とは?
見た目や最新技術に魅かれて性能にお金をかけすぎると、かえって使いにくい家になってしまうこともあります。
たとえば、スマートホーム機能を詰め込みすぎて操作が複雑になり、「かえって不便」と感じる人は少なくありません。
照明やカーテンの音声操作などは、トラブル時の対応が難しいことも。
また、無垢材の床や自然素材の壁、海外製の高級設備などに予算をかけた場合、アフターメンテナンスや後々不具合が出た際の修理・交換が高額になり後悔する人もいます。
最新機能やデザイン性にとらわれすぎず、実際の使いやすさや暮らしとの調和を重視することが大切です。
③ お勧めしたい性能とは?
住宅性能は「高ければ良い」ではなく、「その家族に合っているか」が大切です。
たとえば共働き家庭には、食洗機や浴室乾燥機といった家事を助ける設備や、ムダのない家事動線が優先されます。
在宅ワークが多い家庭なら、空調の効きやすい断熱性や快適な室内環境が重要視されるでしょう。
高齢の家族と暮らす場合は、段差のない設計や浴室の寒暖差対策など、安全面にも配慮した性能が求められます。
それぞれのライフスタイルに合う「ちょうど良い性能」を選ぶことが、本当に価値ある家づくりといえるでしょう。
2.性能は大切。それを超えた価値を実現する家づくり

住宅性能は住まいの基本を支える重要な要素ですが、それだけで「良い家」とは言い切れません。
ここでは、目に見える性能を超えて、暮らしを豊かにする「本当の価値」について考えていきましょう。
(1)本当に大切なものは、目には見えない
断熱性や耐震性などの数値で測れる性能も確かに大切ですが、住まいにとって本当に大切なものは、目に見えない部分にあることが多いものです。
たとえば、「どんなふうに暮らしたいか」「どんな時間を家族と過ごしたいか」といった想いは、数値では表せません。
しかし、その視点を大切にして設計された家は、住む人の心に寄り添い、長く愛される住まいになります。
性能の高さだけでは実現できない、住む人らしさこそが、家づくりの本質といえるでしょう。
(2)住み続けるほど好きになる住まいとは?
住まいに対する満足感は、年月とともに育つものです。
「こんなふうに暮らしたい」という想いから生まれた家は、使い込むほど愛着が深まります。
しかし、大手ハウスメーカーの規格型住宅では、プランがあらかじめ決まっていることが多く、細かな要望に対応できないことがほとんどです。
土地の形状やライフスタイルにもなんとなく合わないまま、妥協した設計になることも少なくありません。
その点、地域に精通した工務店と自由設計で家を建てるのであれば、自分たちの暮らしに合った間取りが実現できます。
気候や土地条件に合った柔軟な設計も可能になり、長く快適に暮らせる家にできるでしょう。
① 注文住宅は「想いを設計に落とし込める」家づくり
注文住宅の魅力は、「わが家の場合はこんな暮らしがしたい」という想いを間取りや設備に反映できることです。
家族のライフスタイルに合わせて動線や収納、趣味のスペース、寝室の大きさなどを自由に設計できるため、既製プランでは叶わない住まいが実現します。
暮らし方から発想する家づくりこそが、注文住宅の本質です。
② 注文住宅と建売住宅の違い
建売住宅は完成済みの物件を購入する形式で、価格が明確で入居までが早いのが魅力です。
ただし、間取りや設備はあらかじめ決まっており、変更ができないため、細かな要望に応えるのは難しいのが実情です。
その点、注文住宅は一から設計できるため、家族構成や暮らし方、趣味や将来の変化まで見据えた家づくりが可能です。
動線や収納、採光の工夫など「自分たちにとって住みやすい家」を実現できるのは、大きな利点といえるでしょう。
③ 注文住宅のメリット&デメリット
注文住宅の最大のメリットは、自由度の高さです。
家族の希望や生活スタイルに合わせて、間取りや仕様を一から決められるため、「自分たちらしい家」が実現できます。
また、素材や設備にもこだわることで、長く快適に暮らせる空間がつくれます。
一方で、打ち合わせや工期に時間がかかる点や、予算管理が難しくなりやすい点はデメリットといえます。
そうした不安を軽減するには、信頼できるパートナーを見つけることが大切です。
④ 自由設計でできること・できないこと
自由設計の注文住宅では、間取りや動線、収納、内装デザインまで柔軟に決められるのが魅力です。
趣味部屋をつくったり、家事動線を徹底的に工夫したりと、生活に合わせた家づくりが可能になります。
ただし、「自由」とはいっても制限はあります。
たとえば、構造上必要な柱をなくすことや、耐震性の基準を下回る設計は認められていません。
また、大手ハウスメーカーでは、注文住宅であっても仕様が細かく規格化されており、傾斜地や変形地などには対応しきれないこともあります。
(3)足立区に住むほど、足立区が好きになる家とは?
足立区での暮らしをもっと豊かに、もっと心地よくするためには、どうすればよいのでしょうか。
ここからは、地域特性を活かしながら、自分たちらしい住まいを実現するヒントを紹介していきます。
① 足立区で“想いのある家づくり”を成功させるために
足立区での家づくりを成功させる鍵は、「どんな暮らしをしたいか」という想いをしっかり設計に落とし込むことです。
単に家を建てるのではなく、地域の特性や家族のライフスタイルに合う「住み心地」を形にする姿勢が求められます。
特に自由設計の注文住宅では、細かな希望を丁寧にヒアリングしてくれるパートナーの存在が重要です。
足立区の事情に精通しており、土地の条件や周辺環境をふまえたうえで想いをかたちにしてくれる工務店と出会えれば、満足度の高い住まいづくりにつながります。
② 地域特性(交通・治安・子育て支援など)
足立区は東京23区の中でも緑が多く、子育てしやすい土地です。
治安についても区民の約6割が「良い」と感じており、とくに住宅街では落ち着いた環境が保たれているのも安心です。
北千住駅周辺のエリアでは都心へのアクセスも良好。近年子育て世代に人気が高まっています。
子育て支援も充実していて、医療費は18歳まで助成されます。
保育にも力を入れており、待機児童ゼロを目指した活動もおこなっています。
公園や緑地も多く、都市と自然が調和した住環境が魅力です。
③ 足立区の土地探しで気を付けたいこと
足立区で土地を探す際には、「狭小地」や「変形地」といった都市特有の条件に注意が必要です。
狭小地とは一般に20坪以下の土地を指し、建て方に工夫が求められます。
さらに、三角形や台形のような「変形地」、奥まった場所に敷地がある「旗竿地」も珍しくありません。
これらの土地は価格が抑えられる一方、間取りや動線に制約が生じやすく、設計力が試されます。
後悔しないためには、地域に詳しく、複雑な土地条件にも柔軟に対応してきた実績が豊富な工務店と一緒に検討することが大切です。
④ 足立区で注文住宅に活用できる補助金や助成金
足立区で注文住宅を建てるときには、国の補助金制度に加え、独自の助成金を活用できる可能性があります。
たとえば足立区の一部の地域においては、耐震性に問題がある木造住宅を建て替えるときに、撤去・解体する費用が最大200万円助成される可能性もあります。
詳しくは、区役所にて確認するようにしてください。
⑤ ローカルな設計・施工に強いパートナー選びのコツ
足立区で家を建てるなら、地域の土地事情や行政手続きに詳しい地元密着型の工務店が心強い存在になります。
狭小地や変形地への対応力、道路状況や近隣環境への配慮など、地元ならではの知見が求められる場面が多いことが理由です。
また、顔の見える関係でしっかり話を聞いてくれるかどうかも重要なポイントです。
住む人の「想い」をくみ取り、柔軟に提案してくれるパートナーなら、設計段階から施工、メンテナンスまで安心して任せられるでしょう。
3.性能だけでは補えない「住みにくさ」の正体と、必要な配慮

今、家づくりの現場では「性能だけで選ぶ時代」は終わりつつあります。
ここからは、住んでから気づく「住みにくさ」の正体と、見落としがちな配慮のポイントを見ていきましょう。
(1)生活動線や高さの不整合など「住む人」への配慮
どれだけ高性能の家でも、住む人の体格や生活習慣に合っていなければ「住みにくい家」になってしまいます。
たとえば、キッチンの高さが合わない、洗濯機から物干し場までが遠いなど、ちょっとした不整合は日々のストレスにつながります。
特に高齢の方や子どもがいる家庭では、段差や手すりの位置、通路の幅など細かな配慮が欠かせません。
見た目のスペックでは見落とされがちな部分こそ、実際の暮らしに直結する大切な要素です。
(2)収納・コンセント・水栓の不足 or 過剰など「暮らし」への配慮
家づくりで意外と多い後悔が、「収納やコンセント、水栓の配置」に関するものです。
足りなければ不便、かといって過剰でも使いにくいという、「ちょうど良さ」が問われる部分です。
たとえば、「ここに収納があれば便利だった」「掃除機の充電場所がない」「庭に水栓があっても使わない」など、実際の暮らしをイメージせずに配置すると、使い勝手に差が出てしまいます。
暮らし方や日々の動作に合わせて考えることが大切です。
(3)採光・通風・音環境など「地域で暮らすこと」への配慮
快適な家づくりには、立地や周辺環境に応じた工夫も重要です。
たとえば、日当たりの悪い土地で南向きの窓にこだわると、プライバシーが確保できなかったり、音の出入りに悩まされたりするかもしれません。
採光や通風、隣家との距離感、周辺の音環境などは、建物の性能では補いきれず、「その土地をどう活かすか」がポイントになります。
地元の事情をよく知るパートナーと相談しながら、環境に合った設計を考えることが、ストレスの少ない暮らしにつながります。
(4)“らしさ”の欠如=愛着が持てない「個性」への配慮
性能や見た目が整っていても、「なんとなく味気ない」「自分の家という感じがしない」と感じることがあります。
それは、住まいに「自分たちらしさ」、つまり個性が反映されていないからかもしれません。
たとえば、思い出の家具がぴったり収まるスペースや、建て替え前の家で使われていた品々の再利用など、些細なこだわりがあるだけで、住まいへの愛着は大きく変わります。
暮らしに寄り添った「自分たちらしさ」を設計に盛り込んで、長く愛せる住まいをつくりましょう。
4.想いを反映させる“自由設計”の家づくりの進め方と施工事例

自由設計は、ただ間取りを自由に決められるだけではなく、「暮らし方」や「想い」をかたちにするプロセスです。
ここでは、自由設計の進め方と、想いが反映された実際の施工事例をご紹介します。
(1)自由設計の家づくりの進め方とポイント
自由設計の家づくりでは、「どんな暮らしをしたいか」という想いを言語化し、それを設計に落とし込むことが大切です。
まずは家族で理想の暮らし方を話し合い、優先順位を整理するところから始めましょう。
それから土地条件や予算、間取りの希望などを設計者とすり合わせつつ、プランを固めていくとスムーズです。
打ち合わせを重ねるなかで、新たな気づきや改善点が見つかることも多く、「話しながらかたちにしていく」プロセス自体が自由設計の醍醐味でもあります。
信頼できるパートナーと二人三脚で進めることで、想いをきちんと反映した家づくりを叶えましょう。
(2)注文住宅で“後悔しない”ためのチェックリスト
注文住宅は自由度が高い反面、判断の連続でもあります。
建てたあとに「こうしておけばよかった」と後悔しないためには、計画段階から以下のようなポイントを押さえておくことが大切です。
- 暮らしの動線は想定通りか?
- 収納量と配置は生活スタイルに合っているか?
- 将来の家族構成やライフスタイルの変化を見越せているか?
- 日当たりや風通し、音環境など、立地に合った設計になっているか?
このような視点を持って一つひとつ確認していけば、住んでからのギャップを防ぎ、満足度の高い家づくりへとつながります。
(3)自由設計を活かした施工事例
ここからは、浅野工務店が手がけた自由設計の実例を紹介していきます。
① 部屋干しスペースや小屋裏収納など、暮らし方に寄り添ったA様邸
まずは、周囲の街並みに調和しながらも、落ち着いた存在感を放つシンプルモダンな佇まいが印象的なA様邸をご紹介します。

花粉症のご家族のために、バルコニーの手前にコンパクトな洗濯物の室内干し場をつくりました。
突然の雨にも対応できるので、忙しい家族にとって心強い味方です。


小屋裏収納は荷物の持ち運びをスムーズにするために、簡易的なハシゴではなく階段にしました。
広々とした空間で、大きなものや季節のものなどを自由なレイアウトで収納できます。

毎日のお買い物の負担をなくすためにキッチン横にパントリーをつくりました。

建て替え前のお家にあった欄間を再利用しました。
住み慣れた家の雰囲気を新しいわが家でも感じられます。
家族の暮らしに寄り添った空間づくりが印象的な住まいです。

② 目の不自由なお母様への思いやりを住みやすさに変えたB様邸
B様邸は14.75坪というコンパクトな間取りで、目の不自由なお母様が安心して暮らせる工夫を詰め込んだ平屋住宅です。
間取りはすべてがワンフロアで完結し、車いすがスムーズに移動できるように玄関までスロープをつくりました。

コンパクトな玄関に車いすが置けるように、玄関収納は置かずに棚と吊戸棚を付けました。

室内は段差をなくしたバリアフリー設計とし、お母様の寝室と台所、そして共用スペースは回遊動線※で移動できます。
※回遊動線とは、家の中をぐるりと一周できるような間取りのこと。動線上に行き止まりがないため、車いすの方もスムーズに移動できます。

特に浴室は、安全性に配慮した設計が光ります。
立ち上がりや移動をサポートする手すりを複数設置し、バスタブには滑りにくい凹凸加工がされているものを選びました。換気乾燥暖房機で冬も暖かです。

少なめの収納を補うために大きな床下収納を付けました。

お母様のためのやさしさと心配りが、目に見えるかたちで丁寧に表現された一棟です。
③ 足立区ならではの土地事情に対応、「想像以上!」と喜ばれたC様邸
狭小地や変形地が多い足立区で、理想の家を実現したC様邸です。

細長い敷地のためにプライベートの空間と共用の空間をわけることが難しいので、生活の場面ごとに使用できるように廊下はつくらず、部屋と部屋の間仕切りの扉を開放感がある折れ戸にしました。


キッチンの奥に浴室をつくることでキッチンと廊下を兼用して使えるようにして無駄なスペースをなくしました。

収納スペースを確保するために設けた小屋裏収納は、居住空間を圧迫せずに収納力をアップする工夫の一つです。


敷地の形状を逆手にとった柔軟な設計で、C様ご家族にぴったりの住まいが完成しました。
④ 梁、神棚、飾り壁など、新しい家に家族の歴史を組み込む工夫も自由自在
建て替え前の物を再利用して新しい家に活かせるのも、自由設計ならではの魅力です。
以前の住まいで大切にされていた梁や神棚、飾り壁などを新しい空間に取り入れ、ご家族の記憶を現代の暮らしへとつなげることが可能です。
こちらは、旧邸の玄関で使用していたものを、新居の階段の柵に再利用したものです。

奥の黒い付け柱は、旧邸の丸太の梁を割いて飾りにしました。

仏間の欄間飾りや扉を再利用しました。

ご家族の思い出の欄間を再利用しました。


信心深いご主人の希望で、旧邸の神棚をきれいにして再利用しました。

単に「新しくする」だけでなく、「残すもの」と「変えるもの」のバランスを見極めることで、唯一無二の住まいをつくってみてはいかがでしょうか。
5.浅野工務店の想い

浅野工務店は、住む人の気持ちに寄り添いながら、その想いを丁寧にかたちにしていく家づくりを大切にしています。
ここでは、私たちの姿勢と、お客様との関わりのなかで育まれてきた考えをご紹介します。
(1)住む人の想いを聞きたい
浅野工務店の家づくりは、「こんな暮らしがしたい」という住む人の想いを出発点にしています。
間取りや設備の要望だけでなく、その奥にある「どんな時間を過ごしたいか」「どんなふうに暮らしたいか」といった気持ちを大切にした設計が特徴です。
実際の打ち合わせでは、ご家族みんなの声を聞くことを重視し、時には家族会議のような時間を設けることも。
そうすれば、「本当に大切にしたいこと」が自然と浮かび上がってくるものです。
想いをくみ取る対話こそが、浅野工務店の設計の原点です。
(2)お金では買えない。見えない家づくりの本当を一緒に考えたい
家づくりでは、目に見える仕様や価格ばかりが注目されがちですが、本当に大切なのは「数字に表れない部分」にあります。
たとえば、動線の工夫や空気感、家族との距離感といった要素は、お金でその価値を測れません。
浅野工務店では、そんな「見えない部分」にこそ丁寧に向き合い、住んでからの心地よさを一緒に考える家づくりを心がけています。
ご家族一人ひとりの希望に寄り添いながら、「本当にいい家とは何か」を一緒に考えていきましょう。
(3)足立区のお客様が『住み続けるほど好きになる住まいに!』、浅野工務店のお約束です
浅野工務店が目指しているのは、「住めば住むほど好きになる家」です。
それは、住みやすさだけでなく、家族の想いがきちんと反映されている家だからこそ生まれるものです。
足立区の気候や土地条件、地域の暮らしに精通している私たちだからこそ、その土地に合った家づくりができます。
住む人の声に耳を傾け、細部まで丁寧に設計・施工する姿勢を大切にしてきました。
お引き渡しがゴールではなく、そこから始まる「長いお付き合い」を大切にすること。愛され続ける住まいにすること。
それが、私たち浅野工務店のお約束です。
6.まとめ

家づくりにおいて「性能」は確かに大切な要素です。
しかし、それだけに終始してしまうと、理想の住まいにはなりません。
暮らしやすさや安心感、そして家族の想いがきちんと反映されてこそ、長く愛される家になるからです。
浅野工務店は、足立区に根差しながら、ご家族の一人ひとりと丁寧に向き合う家づくりを続けてきました。
「数値では測れないけれど、心から納得できる家を建てたい」、そんな想いをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
著者プロフィール
浅野工務店株式会社 代表取締役社長
以来、足立区専門の地域密着型工務店として、お客様の住まいに対する不安や不満を解決することを使命とし、一つ一つの仕事を丁寧に、誠実に取り組んでいます。
足立区ならではの住環境や特性を誰よりも理解しているという自負のもと、地域住民の方々がより快適に暮らせるための提案を行っております。
足立区にしっかりと根を張り、地域の皆様に末永く愛される工務店を目指し、日々精進しています。
- 【最終更新日】2025年07月24日 11:22:41
- 【投稿日】2025年07月24日 11:22:40