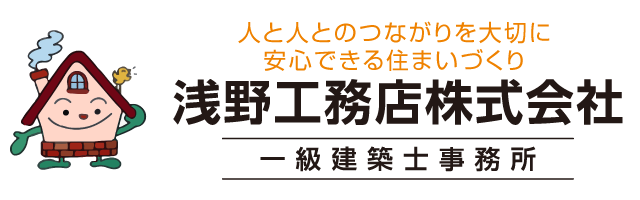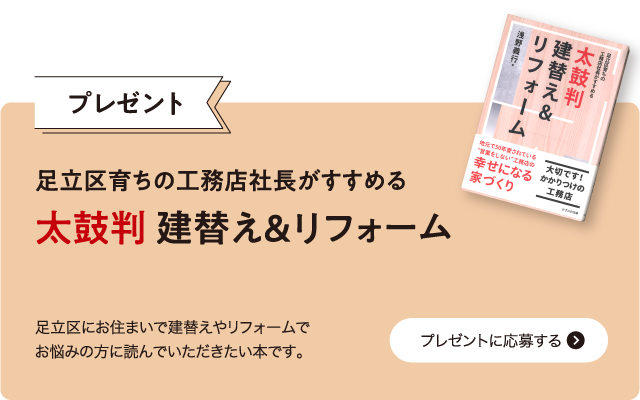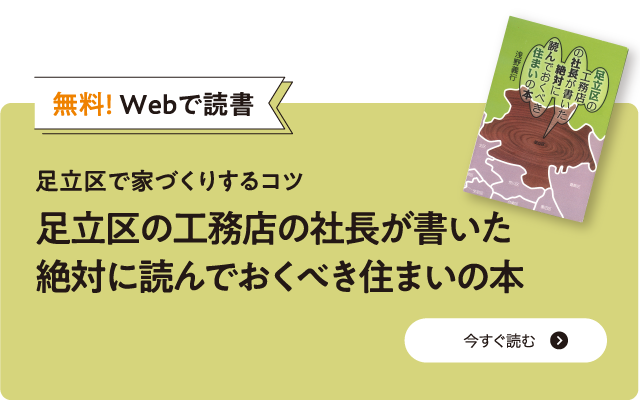【建築基準法改正】足立区で減築リフォームをするメリットは?耐震と省エネの新基準も解説

「住む人が減って、家の中に使わない部屋がある」
「固定資産税を少しでも減らしたい」
「老朽化した家を地震でも安心な家にしたい」
「先々のメンテナンス費用を節約したい」
「コンパクトにスッキリ暮らしたい」
「光熱費を減らしたい」
建築費の高騰が続き、減築リフォームを選択する人が増えています。
使わない部屋を減らす、将来を考えて安全のために平屋にリフォームする……
減築リフォームを選択する人の理由はさまざまです。
また、2025年4月から、いよいよ建築基準法の改正が施行されました。
耐震や省エネの新基準やリフォームの進め方は、どう変わったのでしょう。
この記事では、減築リフォームのメリットと課題、新たに改正された建築基準法に沿う減築リフォームの上手な進め方や注意点などについて解説します。
目次
1.減築リフォームとは?

減築リフォームとは、住まいの一部を取り除き、延べ床面積を小さくする改修工事を指します。
まずは、なぜ今この選択肢が注目されているのか、足立区でのニーズの高まりや背景を見ていきましょう。
(1)足立区の減築リフォームのニーズの高まりと背景
足立区で減築リフォームへの関心が高まっている背景には、人口構成の変化や経済的な事情があると推察されます。
足立区の高齢化率(65歳以上の人口比率)は2023年時点で24.5%に達しました。
今後、2050年には35.3%に上昇すると予測されています。
加えて、1世帯あたりの人員も1.89人まで減少しており、これは単身・夫婦のみの世帯の増加を意味します。
こうした変化により、「必要最小限の空間で快適に暮らしたい」と望む人が増えてきました。
建築コストの上昇や固定資産税の負担を軽くしたいという思いも、減築リフォームを後押しする要因となっていると考えられます。
(2)よくある減築リフォームのきっかけ・減築のスタイル
減築を考えるきっかけは、日々の暮らしの中で感じる「ささいな不便さ」に端を発することが多いようです。
たとえば「使っていない部屋が多い」「2階へ上がるのが大変」「光熱費をもっと抑えたい」などがよくある声です。
また、防犯性や通風・採光の改善を目的に減築することもあります。
スタイルとしては、2階部分をすべて取り除いて平屋にするケースや、一部の部屋だけを減築して生活空間を集約する方法が考えられます。
(3)建築基準法改正で減築リフォームはどう変わる?
2025年4月に建築基準法が改正され、木造2階建て住宅や延べ床面積が200㎡を超える平屋の大規模リフォームをおこなう場合には、建築確認手続きが必要になりました。
具体的には、主要構造部(壁・柱・梁・床・屋根・階段)のいずれかを過半(2分の1)以上修繕・模様替えする場合が対象とされ、減築リフォームにも新たな基準が適用されます。
これにより、耐震性能や省エネ性能に関する要件を満たすよう求められる可能性が高くなります。
たとえば減築によって建物の構造が変わる場合、耐震計算の見直しが必要になったり、断熱材の追加や窓の性能向上などの工事が求められたりすることがあるかもしれません。
減築に際しては、これらの変更点を踏まえ、計画段階から専門家と相談しながら進めることが重要です。
2.減築リフォームのメリット
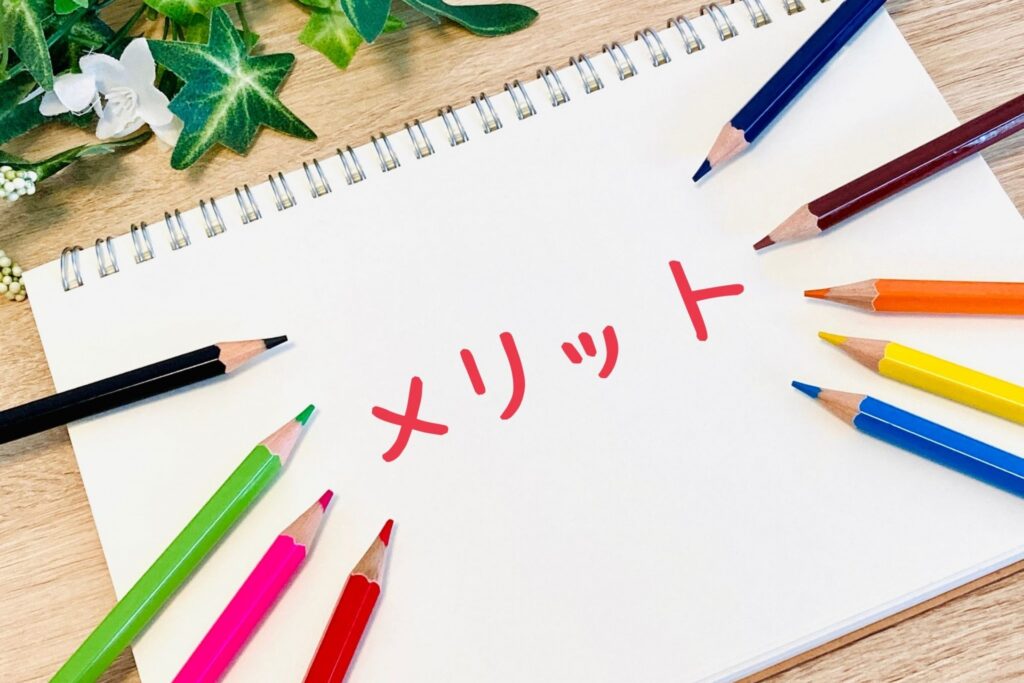
減築リフォームは、ただ家を小さくするだけではありません。
暮らし方や家の使い方を見直すことで、多くのメリットをもたらします。
ここでは、代表的なメリットをいくつかの観点から紹介していきます。
(1)生活快適性の向上
部屋数が多すぎたり、使わない空間があったりすると、日常動線が複雑になりがちです。
減築によって必要な部屋だけを残し、ムダを省いた間取りにすれば、移動のしやすさや家事効率がぐっと高まります。
たとえば、トイレや寝室をワンフロアにまとめると、高齢でも安心して暮らせる住環境を実現できます。
家族の生活パターンに合った空間構成に見直すことで、日々のストレスも軽減され、快適さが向上するのです。
(2)維持費・光熱費の削減
住宅の維持管理にかかる費用や光熱費は、住宅規模に比例します。
そのため、減築リフォームによって家の面積を適正化すれば、冷暖房などに必要なエネルギーも少なくなり、電気代・ガス代の負担が軽減されることがメリットです。
さらに、屋根や外壁の塗装・修繕といった定期メンテナンスが必要な面積も減るため、将来的な維持コストも抑えやすくなります。
生活規模に見合った住まいに整えることは、日々の出費を見直す第一歩といえるでしょう。
(3)耐震性能の向上
減築リフォームは、不要な構造を取り除くだけでなく、建物全体のバランスを見直し耐震性能を向上させる機会にもなります。
特に1981年5月31日以前に建てられた「旧耐震基準」の住宅では、リフォームを機に「新耐震基準」に適合させることで、安全性を大きく向上させることが可能です。
新耐震基準では、震度6強〜7程度の大地震でも倒壊しないことが前提とされており、耐震改修と減築を同時におこなうことで、構造的な安心感を得られます。
耐震化工事に補助金は使える?
多くの自治体では、耐震改修を目的とした工事に対して補助金制度を設けています。
足立区でも、旧耐震基準の住宅を対象に、耐震診断や耐震設計、耐震改修にかかる費用の一部を支援する制度があります。
詳しくは「耐震改修促進事業」をご覧ください。
(4)固定資産税・都市計画税の負担軽減
固定資産税や都市計画税の評価額は住宅の床面積に応じて決まることから、広いほど高くなります。
そのため、減築によって延べ床面積を縮小すれば、これらの税負担が軽減される可能性があるのもメリットです。
特に老朽化した2階部分などを取り除くなど、減築規模が大きいほど、その効果は高まります。
税額の軽減は毎年継続的な効果が期待できるため、家計にとってもメリットが大きいといえるでしょう。
(5)建て替えよりも費用を抑えられる
住宅の全面的な建て替えは、設計費用・新築工事費に加え解体費用も必要になるため、どうしても高額になりがちです。
一方、減築リフォームは既存の構造や基礎を活かしながら、必要な部分だけを更新・縮小するため、工事全体のコストを大きく抑えられます。
工期についても新築よりも短い場合が多く、工事規模によっては仮住まいや引っ越しが不要なケースも少なくありません。
費用面でのハードルを下げながら、暮らしに合った住まいを実現できるのも、減築リフォームの大きな魅力の一つです。
(6)バリアフリーに対応しやすい
減築リフォームは、生活空間を1フロアに集約したり、段差のない間取りに変更したりと、バリアフリー化と非常に相性がよいのも特徴です。
特に高齢者や介護が必要な家族がいる家庭では、玄関やトイレ、浴室の動線を見直すことで日々の暮らしやすさが格段に向上します。
まだ若い世代でも、将来を見据えて安心できる住まいにしたいと考える人にとって、減築は有効な選択肢といえるでしょう。
3.減築リフォームの課題と対策

多くのメリットがある減築リフォームですが、実施にあたっては注意すべき課題も存在します。
ここでは、近年の法改正や住宅性能基準の変化を踏まえたうえで、減築時に直面しやすい課題とその対策について解説します。
(1)断熱性能基準の強化
2025年4月から省エネ基準への適合が義務化されました。
減築リフォームにおいても工事の内容によっては、断熱材の追加や窓の性能向上など、省エネ基準に準じた対応が求められる可能性があります。
具体的には、既存の窓を高性能な断熱サッシに変更したり、壁や床に断熱材を追加したりする工事が必要になることも。
その結果費用が増加する場合もあるため、補助金制度の活用も視野に入れ計画することが重要です。
省エネリフォームに最適な補助金は?
断熱性能の強化が求められるなか、省エネリフォームに対する補助金制度の活用は重要なポイントです。
たとえば、国の「住宅省エネ2025キャンペーン」では、高性能な窓の設置や断熱改修に対して補助が受けられます。
こうした制度については、後述する「減築リフォームに活用できる補助金・助成金」で詳しく紹介しますので、参考にしてください。
(2)耐震基準の強化
減築によって構造に大きな変化が生じる場合、耐震性の再確認が必要です。
特に壁や柱を取り除くと建物全体のバランスが崩れる可能性があるため、屋根・床のバランスを考慮し、構造計算による安全性のチェックが求められます。
また、2025年の建築基準法改正により耐震性能の基準が厳格化され、一定規模以上のリフォームでは新耐震基準への適合が必須となりました。
必要に応じて耐力壁の追加や基礎補強をおこなうなど、耐震設計を含めたリフォーム計画が重要です。
安全性を確保するためには、専門業者との綿密な打ち合わせが不可欠です。
(3)家族構成の変化への対応
長年住み続けた家も、家族構成の変化により使いづらさを感じることがあります。
子どもが独立して部屋が余ったり、親の介護が必要になったり、ライフステージに応じた住まい方の見直しが求められる場面は多いでしょう。
減築リフォームは、そうした変化に柔軟に対応するための手段の一つです。
必要な空間だけを残し、暮らしやすい間取りに再編成することで、無理なく長く住み続けられる住環境を整えられます。
(4)法改正による、手続きや検査の増加と、費用負担の増加
2025年の建築基準法改正により、大規模な減築リフォームでは建築確認申請が必要になるケースが増えています。
申請のためには図面や構造計算書などの提出が求められ、これまで以上に手続きが煩雑になりがちです。
加えて、中間検査や完了検査の対象となることもあり、その対応にも時間と費用がかかることもあるでしょう。
これにより設計費や申請費用が増加し、想定よりもリフォーム費用が膨らむことが考えられます。
事前に専門家と相談し、必要な手続きやコストを把握しておくことが重要です。
4.よくある減築リフォーム例と進め方

減築リフォームとひと口にいっても、目的や規模によって内容はさまざまです。
ここでは、実際によくある3つの方法と進め方のポイントなどを見ていきましょう。
(1)[リフォーム例①]使わなくなった部屋を減築し、固定資産税の削減
よくあるのは、子どもが独立して使わなくなった2階の一部や、平屋の一部スペースを撤去して、居住面積を縮小するタイプのリフォームです。
こうした減築によって建物の延べ床面積が減れば、固定資産税や都市計画税の評価額が見直され、税負担の軽減につながる可能性があります。
工事の内容は、屋根や外壁の部分解体、断熱補修、外構まわりの調整などが中心です。
(2)[リフォーム例②]2階を減築し平屋に。介護保険を活用しバリアフリーリフォーム
高齢になり2階への移動が負担となったときや、家族の人数が減ったときによくおこなわれるのが、2階部分を撤去して平屋にする減築リフォームです。
このケースでは、玄関やトイレ、浴室などに手すりを設置したり、段差を解消したりする、バリアフリー改修が同時に実施される傾向があります。
(3)[リフォーム例③]耐震改修補助金を活用して安全な住まいに減築
築年数が古く、耐震性に不安のある住宅では、耐震性を高めるために減築をおこなうケースも多く見られます。
たとえば、2階建て住宅の2階を取り除いて平屋にし、構造バランスを整えたうえで耐震補強を実施するパターンです。
(4)減築リフォームの進め方
減築リフォームを成功させるためには、まず「なぜ減築したいのか」という目的を明確にすることが大切です。
生活動線の改善、耐震性や省エネ性の向上など、目的に応じて工事の優先順位や内容、規模などが変わってくるためです。
次に、信頼できる施工業者に相談し、現地調査をもとに具体的なプランと見積もりを出してもらいましょう。
法規制や補助金の対象条件も早めに確認することで、スムーズに計画を進められます。
(5)減築リフォームの注意点やポイント
減築リフォームでは、構造バランスの変化に十分注意する必要があります。
壁や柱を取り除くことで、建物全体の強度が低下するおそれがあるため、耐震性への影響を事前に確認することが重要です。
また、減築部分の断熱性や防水処理が不十分だと、室内環境に悪影響を及ぼすケースもあります。
減築による資産評価の変動や、登記の変更が必要になることも多いので、減築リフォームの実績が豊富な工務店に相談することが重要です。
5.減築リフォームに活用できる補助金・助成金

減築を含むリフォームでは、内容に応じて国や自治体の補助制度が利用できる可能性があります。
ここでは代表的な制度を簡単に紹介します。(2025年4月時点の内容に基づいています。詳細は各公式サイトや自治体窓口でご確認ください。)
(1)2025年度の足立区のリフォーム補助金
省エネリフォーム補助金
足立区内の既存住宅で、省エネ化を目的に、ガラスや窓の交換、内窓の新設などのリフォームをした場合に、上限5万円まで補助される制度です。
補助対象工事の請負業者が足立区内の業者であるなど、そのほかさまざまな条件があります。
住宅改良助成制度
足立区内の全世帯を対象に、世帯人員の増加にともなう間取り変更や屋根の軽量化、耐震ドアの設置などに対し、最大30万円まで助成する制度です。
(2)住宅省エネ2025キャンペーン
高断熱窓への交換や断熱材の追加など、主に省エネ性能を高めるリフォームが対象で、以下の2つの事業が用意されています。
| 事業名 | 対象リフォーム | 最大補助額 |
| 子育てグリーン住宅支援事業 | 省エネリフォームや子育て対応リフォーム | 60万円/戸 |
| 先進的窓リノベ2025事業 | 開口部の断熱性能を向上させるリフォーム | 200万円/戸 |
(3)耐震改修促進事業
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された、旧耐震基準の木造住宅が対象の制度です。
自治体によって内容が異なり、たとえば足立区では、耐震診断の費用に対しては最大30万円、耐震改修工事には最大150万円が助成されます。
(4)長期優良住宅化リフォーム推進事業
耐震・省エネ・劣化対策などを組み合わせた高性能リフォームが対象の制度です。
令和6年度には、評価基準に応じて、最大210万円(子育て世帯などの加算含む)まで補助されました。
長期優良住宅化リフォーム推進事業(参考:令和6年度)
(5)介護保険を活用したバリアフリーリフォーム
要支援・要介護認定を受けた方を対象に、手すりの設置や段差解消、滑りにくい床材への変更などのバリアフリー工事に対し、介護保険から住宅改修費が支給されます。
支給限度額は原則1人あたり20万円で、支給額の上限は9割の18万円です。
(6)既存住宅の断熱リフォーム支援事業
一定の断熱性能を満たす改修工事(外壁・床・屋根・開口部等)を対象とした事業です。
工事内容に応じて、最大120万円/戸まで補助されます。
6.まとめ

使わなくなった部屋の見直しや生活動線の改善、老後の暮らしへの備えとして、減築リフォームを選ぶ方が足立区でも増えています。
耐震・断熱性能の向上、固定資産税や光熱費の削減といったメリットがある一方で、制度改正にともなう手続きや性能基準の確認など注意点もあります。
設計や法務にも配慮が必要なため、経験豊富な工務店に相談するのが安心です。
浅野工務店は足立区で1967年に創業して以来、地域密着の家づくりをおこなってきました。
減築リフォームの実績も豊富ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
著者プロフィール
浅野工務店株式会社 代表取締役社長
以来、足立区専門の地域密着型工務店として、お客様の住まいに対する不安や不満を解決することを使命とし、一つ一つの仕事を丁寧に、誠実に取り組んでいます。
足立区ならではの住環境や特性を誰よりも理解しているという自負のもと、地域住民の方々がより快適に暮らせるための提案を行っております。
足立区にしっかりと根を張り、地域の皆様に末永く愛される工務店を目指し、日々精進しています。
- 【最終更新日】2025年05月01日 16:04:57
- 【投稿日】2025年04月28日 10:15:22